
拘禁刑が言い渡された場合には、刑務所に入らなければなりません。ただし、刑の全部の執行猶予が付された場合は、直ちに刑務所に入るということはありません。
また、刑の一部の執行猶予が付された場合は、言い渡された刑期のうち、執行を猶予された期間を差し引いた期間について、刑務所に入ることになります。

拘禁刑が言い渡された場合には、刑務所に入らなければなりません。ただし、刑の全部の執行猶予が付された場合は、直ちに刑務所に入るということはありません。
また、刑の一部の執行猶予が付された場合は、言い渡された刑期のうち、執行を猶予された期間を差し引いた期間について、刑務所に入ることになります。
「執行猶予」には、刑の全部の執行猶予と刑の一部の執行猶予があります。
以前に拘禁刑に処せられたことがないなど一定の条件を満たす場合に、判決で3年以下の拘禁刑を言い渡すとき、情状により、刑の全部の執行(刑務所に入ること)を1年から5年の範囲で猶予することができます。
また、同様に3年以下の拘禁刑を言い渡すとき、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要かつ相当である場合に、その刑の一部の執行を1年から5年の範囲で猶予することができます。
したがって、猶予されている期間は、刑務所に入ることはありません。
しかし、「猶予」ですから、その期間内に再び犯罪を犯すなどしたときは「猶予」が取り消され、刑務所に入ることとなります。

裁判が確定した時点で勾留されていない場合は、検察庁から刑の執行のための呼び出しがありますので、出頭することになります。出頭した後、刑務所に入り、刑が始まります。
なお、拘禁刑以上の刑が言い渡された後は、裁判確定の前後を問わず、裁判所の許可を受けずに出国することは禁止されています。
有罪判決を受けた際、被告人に対して訴訟費用の負担を命じられる場合があります。
この「訴訟費用」は、主に証人に支払った旅費や国選弁護人に支給された報酬等です。
訴訟費用の負担を命じられた人が、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判確定後20日以内に、裁判所に対し訴訟費用の執行の免除を申し立てることができます。
裁判所において、申立てに理由があると判断し、訴訟費用の執行免除決定がなされた場合は、納付する必要はありません。
罰金は裁判により刑罰として科せられたものであり、必ず、所定の期間内に検察庁に納付しなければなりません。
罰金は、法令に定められた刑罰であることから、刑に服すること(罰金の納付)は、裁判を言い渡された者の義務です。
罰金などの徴収金を任意に納付しない場合は財産に対し強制執行を行います。
また、罰金・科料を納付せず、強制執行をすべき財産がない場合には、労役場に留置されることになります。
「労役場留置」とは、資力がないなどの理由により罰金・科料を納めない場合、その人を刑務所(刑事施設内の労役場)に留置して作業をさせることをいいます。
留置される日数は裁判で決められますが、現在、多くの裁判において1日の留置を罰金5,000円相当と換算されており、その場合には罰金20万円であれば40日間となります。
最長の期間は2年間です。
罰金は、刑罰ですから、定められた期間内に一括して納付しなければなりません。
定められた期間内に納付できないときは、納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」にお尋ねください。
罰金は、検察庁が指定する方法で検察庁指定の金融機関に納めるか、又は検察庁に直接納めることになります。
詳しいことは、通知をした検察庁の「徴収事務担当者」にお尋ねください。
納付された罰金は、没収物と同様、国庫に帰属し、国の予算として使われることとなり、検察庁が独自で使うことはありません。
なりません。
押収された証拠品のうち、没収の言渡しがあった証拠品、所有者が所有権を放棄した証拠品については返還されません。
他方、証拠品の所有者等が返還を希望しているときには還付(返還)しますし、事件終結前であっても、裁判に必要のない押収物等については、還付又は仮還付の手続をとる場合もあります。
原則として、押収物還付公告令に基づき、「押収物還付公告」の手続がとられます。
公告の方法は、検察庁の掲示場に掲示して行い、必要があるときには官報にも掲載します。
なお、公告の結果、所有者等が判明しなかった証拠品は国庫に帰属し、没収物と同様に処分されます。
有価物は売却処分され、その代金は国庫に帰属します。
通貨等も同様で、検察庁が独自に使うことはできません。
無価物は廃棄又は破壊されます。
所有権放棄された押収物についても同様です。
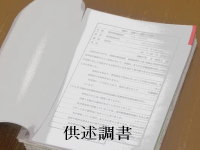
刑事裁判が終了した事件の確定記録や判決書は、閲覧することができますが、法律により閲覧が制限されることがあります。
具体的な閲覧の手続については、これら確定記録や判決書を保管している検察庁の「記録事務担当者」にお尋ねください。