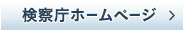警察は刑事事件の第一次的な捜査を行い、検察庁は起訴・不起訴を決定するための捜査を行います。
日本では、起訴は検察官にのみ与えられた権限であり、警察官は起訴できないことになっています。
したがって、検察官は裁判所に対し起訴してその処罰を求めるという責任があるため、警察からの捜査記録などを確認するだけではなく、その内容が真実であるかどうかを、事件の当事者から必要に応じて直接事情を聞くなどして、積極的に自ら事件の真相解明に努力しています。
捜査について
検察庁の捜査と警察の捜査の違いはなんですか?
検察庁の捜査は、具体的にはどういうことをするのですか?

被疑者の取調べや被害者・参考人など関係者からの事情聴取、証拠品の捜索・差押え、さらにその分析・検討などを行います。
警察で事情を聴かれて調書を作成したのに、また、検察庁に呼ばれて事情を聴かれたり、調書を作成したりすることもあるのですか?
検察官は、起訴・不起訴を決定するため、改めて被害者等から事情を聴く必要がある場合があります。御迷惑をおかけしますが、適正妥当な処分を行うためですので、御協力ください。
逮捕されるとどうなるのですか?

身柄が拘束されますが、いつでも弁護人を選任することはできます。
逮捕後、長くても72時間以内に検察官による勾留請求・起訴・釈放のいずれかの手続がとられます。
検察官による勾留請求を裁判官が認めて勾留されると、更に拘束が継続されますが、一部の罪を除き最も長い場合で勾留請求後20日間以内に、検察官は勾留中の被疑者を起訴するか釈放するかしなければなりません。
また、接見禁止の決定がなされると、弁護人以外の人との面会ができなくなります。
検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?

被疑者が犯罪を犯したことが証拠上明白であり、その訴追が必要であると判断した場合に、裁判所に起訴状を提出して起訴します。
不起訴になるのは、主に次のような場合です。
- 訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡したとき、親告罪について告訴が取り消されたときなどは、訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となります。 - 被疑事件が罪とならない場合
被疑者が犯罪時14歳に満たないとき、犯罪時に心神喪失であったときなどは、被疑事件が罪とはならず不起訴となります。 - 犯罪の嫌疑がない場合
被疑者が人違いであることが明白になったときなど、犯罪の嫌疑がない場合は、もちろん不起訴となります。 - 犯罪の嫌疑が不十分の場合
捜査を尽くした結果、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは、不起訴となります。 - 起訴猶予の場合
被疑者が罪を犯したことが証拠上明白であっても、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重と情状、犯罪後の情況などにより検察官が訴追を必要としないと判断した場合は、起訴を猶予して不起訴とすることがあります。
「特捜部(特別捜査部)」って何ですか?
特捜部は、東京・大阪・名古屋の地方検察庁にだけ置かれている部で、公正取引委員会・証券取引等監視委員会・国税局などが法令に基づき告発をした事件について捜査をしたり、汚職・企業犯罪等について独自捜査を行ったりしています。
また、上記三庁以外の主要道府県の地方検察庁にも独自捜査をする特別刑事部が置かれています。
「被疑者国選弁護人制度」って何ですか?
勾留状が発せられた被疑者が、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、裁判官に対し国選弁護人の選任を請求できる制度です。