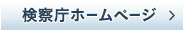検察庁は、明治以来、検事局として裁判所に付置されていましたが、昭和22年5月3日、日本国憲法とともに施行された「検察庁法」により、裁判所から分離して独立し、検察官の行う事務を統括するところとして、現在の検察庁が設けられました。
検察庁について
最終更新日:2015年7月21日
検察庁のなりたち
検察庁の組織と役割

検察庁には、最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁の4種類があり、裁判所に対応して置かれています。
検察庁では、検察官・検察事務官などが執務しており、検察官は、刑事事件について、捜査及び起訴・不起訴の処分を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、刑の執行を指揮監督するなどの権限を持っているほか、公益の代表者として民法など各種の法律により数多くの権限が与えられています。
検察官の仕事
◆犯罪の捜査
検察官には、検事と副検事がいます。
検察官は、法律に違反した犯罪や事件を調べて、その犯人を裁判にかける、とても重要な仕事をしています。
事件が起きると、まず警察が犯人を探して逮捕したり証拠を集めたりする捜査をします。
そして、その疑われている人が本当に犯人かどうか確かめて、罰を与えるための裁判にかけるかどうかを決めます。
裁判にかけることを「起訴」といい、起訴がないと裁判も始まりません。
検察官は起訴をするために、警察と協力をして自分でも捜査を行い、その真実がなにかを明らかにします。
日本では、検察官だけが犯人を起訴する権限を持っています。
犯罪を犯した人に罰を与えるためには、絶対に検察官が必要であり、それだけに検察官の責任は大変重いものなのです。
◆裁判所での公判
検察官は、起訴した事件について、証拠により証明しようとする具体的な犯罪事実を明らかにします。これを「冒頭陳述」といいます。その上で、裁判所に証拠を提出して、被告人が有罪であることを証明します。また、事実及び法律の適用についての意見を述べます。これを「論告」といいます。その際、検察官が相当と考える刑罰についても意見を述べるのが普通です。これを「求刑」といいます。裁判所は、被告人が有罪であることが証明されたと判断すると、「判決」で、被告人が犯した罪の重さに応じた「刑罰」を決めます。このような判決を「有罪判決」といいます。
◆裁判の執行
裁判で決まった懲役・禁錮等の自由刑や罰金などの財産刑は、検察官の指揮により執行します。
検察事務官の仕事
検察事務官は、検察官の指揮を受けて犯罪を捜査、逮捕状による逮捕、事件の証拠品の管理、罰金の徴収などの事務を行うほか、総務・会計などの事務を行っています。
山形地方検察庁の職場と仕事
地方検察庁の長は「検事正」と呼ばれます。
検事正の下に、仕事の内容によっていろいろな部門に分かれて多くの人が仕事をしています。
また、最上、置賜及び庄内地方など山形市から離れた4つの市(新庄、米沢、鶴岡、酒田)には「支部」があり、それぞれの地域の刑事事件に関する仕事をしています。
検察庁Q&A
検察庁に関する質問については、検察庁ホームページ内「Q&Aコーナー」をご参照ください。