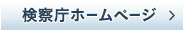令和7年11月20日(木)、高知大学において出前教室を行いました。
今回の出前教室は、高知大学地域協働学部の玉里教授からの依頼を受け、同学部の授業の1コマとして実施したもので、玉里教授と同学部生74名に参加いただきました。
講師の筒井副検事から、「検察庁の業務内容」「特殊詐欺事件の手口や注意点」「社会復帰支援及び被害者支援の現状と課題」「インターネット社会における犯罪の罠」「検察庁職員になるには」などについて説明を行いました。
「地域福祉論」の授業ということで、特に社会復帰支援に関して、検察庁において、福祉機関等と連携してどのような取組がなされているか、実例を交えながら詳しく説明しました。
これに関連して、出所者の就労支援等を行う「職親プロジェクト」の四国高知県支部長である楠瀬武司さんにも同席いただき、楠瀬さんから、職親プロジェクトの歴史や取組内容についてお話しいただくとともに、学生への熱いメッセージが伝えられました。
また、大学生にも身近な問題として、最近多発している特殊詐欺や、軽い気持ちで手を染めかねない口座売買等の犯罪への注意喚起を行いました。そして、情報感覚を磨き、他人を思いやり、自分の行動がどのような結果をもたらすかを想像することが大切であり、それがひいては犯罪に泣く人を減らし、社会を良くすることに繋がると説明しました。
授業後には、学生から「社会復帰支援が犯罪を減らすことにも繋がることなど、その意義や必要性を知ることができた」「身近な犯罪の罠について知り、自分の行動を見直す機会になった」「職親プロジェクトの誰も見捨てないという姿勢はもっと広がるべきだと感じた」などの感想をいただきました。
【出前教室の状況】


当庁では、今後も「出前教室」や「移動教室」などを通じて検察庁に関する広報活動を行っていきますので、希望される場合は当庁まで御連絡ください。
広報活動について
最終更新日:2025年12月4日
最新の広報活動の情報を皆様にお届けします!
是非、ご覧ください。
- 【R7.11.20】高知大学地域協働学部で出前教室を行いました。
- 【R7.10.26】土佐市立高岡中学校で出前教室を行いました。
- 【R7.10.24】高知県立春野高等学校で出前教室を行いました。
- 【R7.9.2】高知健康科学大学の皆さんに移動教室を行いました。
- 【R7.6.30】高知健康科学大学で出前教室を行いました。
- 【R7.6.4】高知県立大学で出前教室を行いました。
- 広報活動の申込み・問い合わせ先について
【R7.11.20】高知大学地域協働学部で出前教室を行いました。
【R7.10.26】土佐市立高岡中学校で出前教室を行いました。
令和7年10月26日(日)に、土佐市立高岡中学校で出前教室を行いました。
今回の出前教室は、同校において例年実施されている「校内ハローワーク」というイベントでの講師のお誘いを受け、初めて参加させていただきました。
このイベントは、全校生徒を対象として、多種多様な職種の方々が講師となり、各講師ごとに割り当てられた教室等において、それぞれの仕事について2講座説明を行うというもので、1講座に20名程度の生徒が集まってくれました。
この日は、当庁を含め19種もの幅広い職種の方たちが参加されておりました。
当庁の説明では、「検察庁及び職員の種類」、「刑事事件の流れと検察庁の仕事」、「検事・副検事・検察事務官になるために必要な条件」などについて説明を行った後、同校の卒業生である当庁職員から、「中学生・高校生の時にやっておいた方が良いこと」、「高知地検の魅力」について説明を行いました。
このイベントは、生徒たちが将来就職するための選択肢を広げる目的で実施されており、大変有意義なイベントだと共感しました。
このイベントを通じて、検察庁のことを少しでも知ってもらい、将来、検察庁に就職希望をしてくれる生徒が現れてくれれば、大変嬉しく思います。
学校関係者の皆様、イベントに参加させていただきまして、誠にありがとうございました。
次回もお誘いいただけるようでしたら参加させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
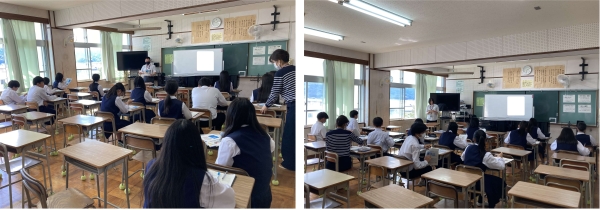
当庁では、今後も「出前教室」や「移動教室」などを通じて検察庁に関する広報活動を行っていきますので、希望される場合は当庁まで御連絡ください。
【R7.10.24】高知県立春野高等学校で出前教室を行いました。
令和7年10月24日(金)に、高知県立春野高等学校で出前教室を行いました。
今回の出前教室は、同校から「1年生の生徒に対して、SNSに関連する犯罪や被害の実態、犯罪を犯してしまった場合におけるその後のことなどについて筒井副検事に講義をお願いしたい。」との依頼をいただき、実施したものです。
当日は、生徒126名と教員10名の合計136名もの方々に参加していただきました。
筒井副検事は、まず、成人による刑事事件の流れに沿って検察庁の業務を説明し、次に特殊詐欺事件の手口を説明しつつ、刑事事件の流れを理解しておけば特殊詐欺事件の被害を防止できることなどを説明しました。
その後、法律の存在意義や、インターネット上において悪気がなく又は無意識のうちに書き込みをするなどの行為が犯罪に該当する可能性があり、犯罪を行った場合における様々な責任(ペナルティ)を負わなければならなくなることなどを説明しました。
最後に、幾つかの設問を紹介し、それらの行為を行った場合におけるその後の予想される展開についても説明を行いました。
今回の出前教室では、生徒の皆さんが、普段身近に接しているインターネットに関連する内容の説明をさせていただきましたので、多くの方々に理解していただけたのではないかと思います。
帰庁後、学校からは、出前教室に参加した生徒の感想を送付していただき、その中には、「今日の講演を受けて、改めてSNSの闇の部分を実感した。今後、自分たちがインターネットやSNSを扱っていく中では、避けては通れないと思うので、しっかりとした理解と知識を得て、加害者にも被害者にもならないようにしたい。」との記載があり、まさに筒井副検事が伝えたかったことがズバリ伝わっていたので、出前教室が実施できて良かったと感じました。
生徒の皆さんは、今後、家族や友人・知人などと知識を深め合って、インターネットを有効活用していただきたいと思います。
最後に、学校関係者の皆様、今回はこのような場を設けていただきまして、本当にありがとうございました。
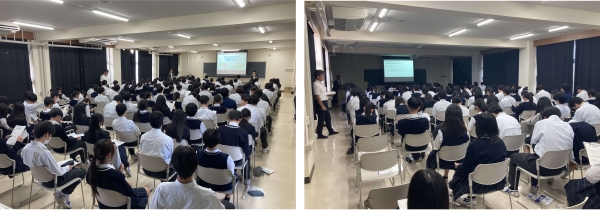

当庁では、今後も「出前教室」や「移動教室」などを通じて検察庁に関する広報活動を行っていきますので、希望される場合は当庁まで御連絡ください。
【R7.9.2】高知健康科学大学の皆さんに移動教室を行いました。
令和7年9月2日(火)、当庁において、高知健康科学大学の皆さんに移動教室を行いました。
今回の移動教室は、同大学の石附教授からの依頼を受けて実施したもので、同大学生5名、同大学教員6名、同大学事務員1名の方たちに参加いただきましたが、その中には宮口学長もいらっしゃいました。
講師は水本検事正が担当し、「検察庁の役割・種類・組織」、「刑事事件の流れ」、「警察と検察の違い」などについて、経験談や実例を交えながら説明を行いました。
その中で、水本検事正は、「検察庁は、罪を犯した全ての人に対して厳罰を与えようとしている訳ではなく、罪に見合った刑罰を求めたり、場合によっては起訴を猶予(不起訴に)したりしています。」などとも説明を行いました。
また、実例を紹介しつつ、「逮捕状が出ているとだます手口の詐欺」といった特殊詐欺事件にも注意するよう呼びかけました。
講義終盤には、参加された方から「刑務所に入っている人が出てきたら恐怖を感じる場合もあるが、刑務所を出所する際の通知などがあるかどうか知りたい。」、「特に大きな事件の場合、起訴から裁判が始まるまでの期間が長い場合もあるが、その期間や流れなどはどのように決まっているのか教えてほしい。」との質疑をいただきましたので、その質疑に対して水本検事正からそれぞれ詳しく説明を行いました。
引き続き、刈谷副検事から、刈谷副検事が担当する公判(裁判)事件の説明が行われた後、その事件の公判傍聴を行いました。
最後に、取調室や装備品、記録庫、証拠品庫の見学などを行いました。
移動教室終了後には、石附教授から「来年度から授業などで見学のお願いをさせて頂くことになると思います。」とのありがたいメールをいただきました。
喜んで実施させていただきますので、お気軽に御相談ください。
【移動教室の状況】
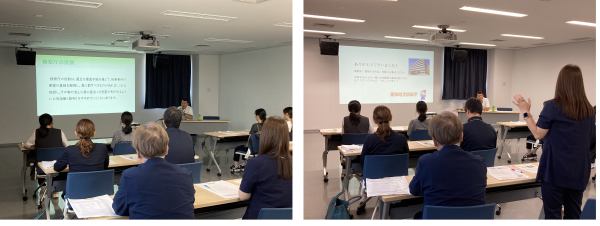

当庁では、今後も「出前教室」や「移動教室」などを通じて検察庁に関する広報活動を行っていきますので、希望される場合は当庁まで御連絡ください。
【R7.6.30】高知健康科学大学で出前教室を行いました。
令和7年6月30日(月)に、高知保護観察所とともに高知健康科学大学で出前教室を行いました。
同大学での出前教室は、昨年に引き続いて2回目の実施となりますが、今回は、同大学1年生及び同大学関係者合計約60名もの方に参加していただきました。
講義は、刈谷副検事から「検察庁の役割」、「検察庁の職員」、「刑事手続の流れ」、「刑執行の流れ」、「警察と検察の違い」などについて説明を行った後、筒井副検事から「社会復帰支援の現状と課題」、「被害者支援の現状と課題」、「インターネット社会における犯罪の罠」をテーマとする内容などについて、実例を交えながら説明を行うとともに、特殊詐欺事件の手口などを紹介しつつ、事件に関与したり、被害に遭わないよう注意を呼びかけました。
質疑・応答では、学生からの質疑に加え、宮口学長からも質疑をいただきました。
今回の出前教室実施に当たり、大学関係者の皆様の御尽力・御協力を賜り、また、学生たちも熱心に聴講していただきましたことに感謝申し上げます。

当庁では、今後も「出前教室」や「移動教室」などを通じて検察庁に関する広報活動を行っていきますので、希望される場合は当庁まで御連絡ください。
【R7.6.4】高知県立大学で出前教室を行いました。
令和7年6月4日(木)に高知県立大学で出前教室を行いました。
今回の出前教室は、同大学田中康代講師の御厚意によって、授業の1コマを当庁水本和彦検事正が使用させていただき、実施したものです。
当日は、42名もの学生たちに加え、報道関係者の方にも参加していただきました。
水本検事正は、「検察庁の役割・種類・組織」、「刑事事件の流れ」、「警察と検察の違い」などについて、経験談や実例を交えながら説明を行いました。
その中で、水本検事正は、「取調べは、被疑者に罪を認めさせることが重要なのではなく、被疑者が本当に罪を犯したのかどうか、罪を犯したのであればなぜ罪を犯したのか、どのような生活を送っていたのか、今後はどうするつもりなのか、といったことを聞くことが重要なのです」と説明を行いました。
さらに、「裁判員裁判」、「被害者支援」、「再犯防止・社会復帰支援」などについても説明を行いました。
また、学生たちに対し、「逮捕状が出ているとだます手口の詐欺」の実例を紹介しつつ、特殊詐欺事件にも注意するよう呼びかけも行いました。
参加した学生からは、報道関係者に対し、「検察官の仕事について理解できた」、「検察官に魅力を感じた」といった感想を話してもらい、報道関係者の方からも、「今まで知らなかったことを今日知ることができました」との感想をいただきました。
今回は、田中康代講師を始め大学関係者の方々の御厚意・御尽力を賜り、また、学生たちも熱心に聴講していただきましたことに感謝申し上げます。
【出前教室の状況】

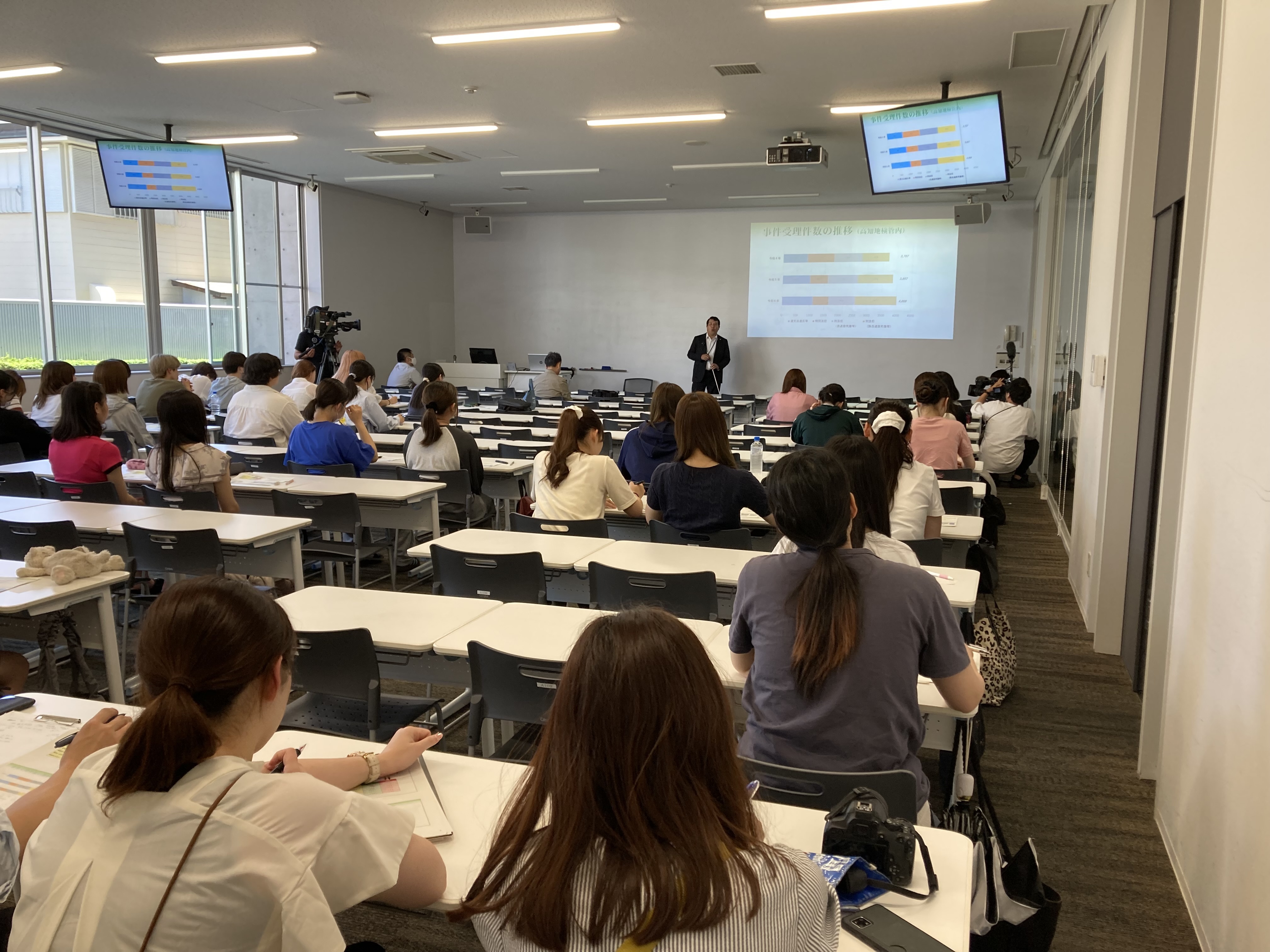
当庁では、今後も「出前教室」や「移動教室」などを通じて検察庁に関する広報活動を行っていきますので、希望される場合は当庁まで御連絡ください。
広報活動の申込み・問い合わせ先について
お気軽にお問合せください。
連絡先 高知地方検察庁企画調査課
電話:088-872-9191(内線2623)
〒780-8554 高知市丸ノ内1丁目4番1号 高知法務総合庁舎

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。