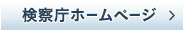検察庁の仕事
最終更新日:2015年3月13日
1捜査
犯罪が発生すると,通常,警察が捜査を行い,被疑者を検挙して検察庁に送ります(送致)。
警察から事件の送致を受けた検察官は,自ら被疑者などを取り調べるとともに,警察に対し,事件処理に当たって必要な捜査を指示したりします。
一方,特捜部が取り扱う事件(例えば国会議員による贈収賄事件など)のように,検察官が自ら犯罪捜査を開始し,被疑者を検挙することもあります(独自捜査)。
2事件処理
検察官は,被害者や目撃者の方から事情を聞いたり,被疑者を取り調べるなどの捜査を慎重かつ十分に行った上で,事件を起訴するか不起訴にするかの処分を決めます。起訴処分には,法廷で公判の開かれる公判請求と,公判が開かれずに書類審査で刑罰(罰金など)が言い渡される略式請求があります。
事件処理に当たっては,無実の人間が罰せられることのないように,十分な証拠があり,確実に有罪判決が得られると判断した場合のみ起訴することとしています。
一方で,有罪判決を得られるだけの十分な証拠があっても,被疑者に有利な事情も最大限考慮した上,例えば,被疑者の改善更生のためには,刑罰を科さない方が適切であると判断したときなどは,裁量により起訴しないこともあります(起訴便宜主義)。
これは,検察官が,その職責上,「公益の代表者」であり,すべての被疑者を処罰すれば足りるというわけではなく,被疑者の改善更生の可能性等も考慮して,大局的見地から判断することが求められているからです。
3裁判
検察官は,公判請求した事件に立ち会い,裁判所に証拠の取り調べを請求したり,証人尋問を行ったりして,被告人が罪を行ったことを証明し,最後に,事件に対する意見を述べて求刑(論告)を行います。
4刑の執行
検察官は,死刑,懲役刑,罰金刑などの裁判の執行を指揮します。