JPEC設置の背景
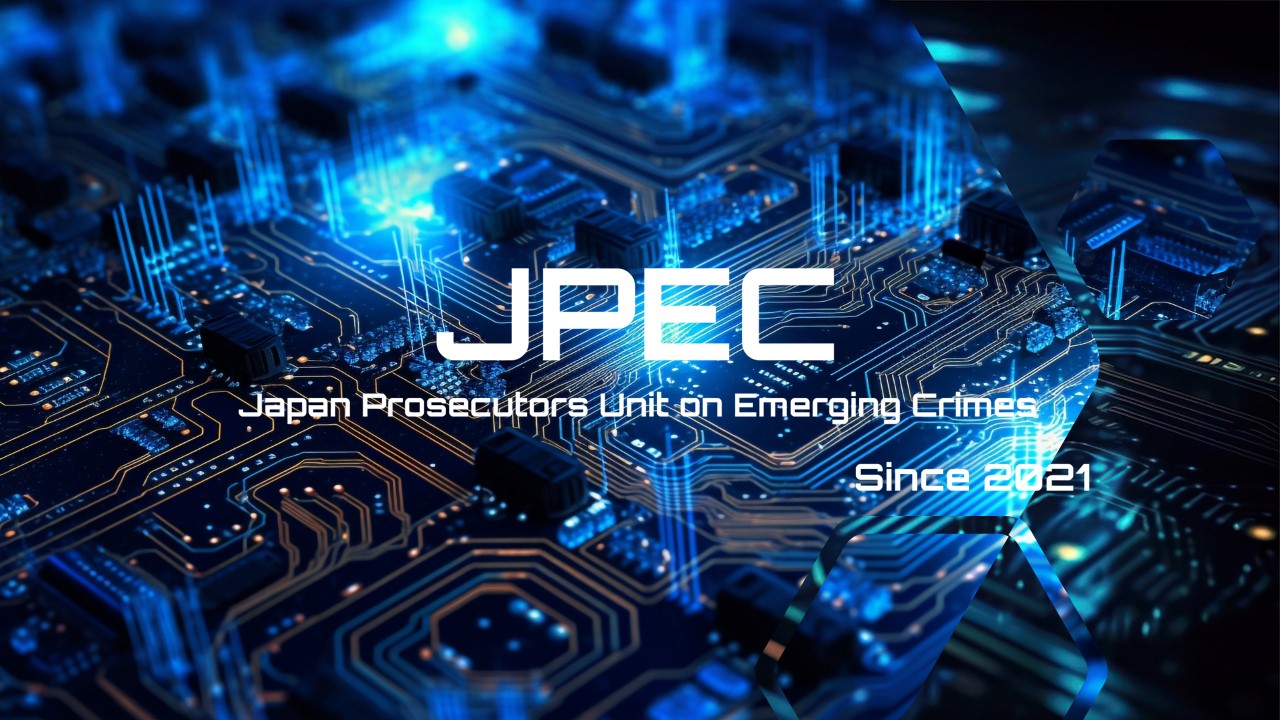
デジタル技術や情報通信技術の加速度的な発展は、私たちの生活を豊かにする一方で、犯罪をより多様化・複雑化させており、スマートフォンやパソコンを利用した犯罪、サイバー空間での国境を越えた犯罪、暗号資産を悪用した犯罪などが頻発し、犯罪の匿名化や広域化も顕著になっています。
このようなデジタル技術や情報通信技術が用いられた犯罪(先端犯罪)の真相を解明し、刑罰権の適正な行使を実現するためには、情報通信技術等に関する高度な専門的な知識・技術と、最新の捜査手法を活用することが必要不可欠です。
そこで、検察庁は、これらの新たな脅威に組織全体で的確に対応する能力を一層向上させるため、令和3年4月1日、「JPEC(Japan Prosecutors Unit on Emerging Crimes)」を設立しました。
JPECは、東京と大阪に設けられたデジタルフォレンジック専門部署(DFセンター)も包含する全国的なネットワークを活かして、業務に当たっています。
JPECの目的
- 先端犯罪(情報通信技術が手段として用いられた犯罪等)の解明に有益な情報の収集・管理・提供
- 先端犯罪の捜査・公判の支援
JPECの主な活動内容
事例集約・情報提供

全国で発生した先端犯罪の事例や官民関係団体が有する最先端の技術的知見を積極的に収集・分析した上、全国の検察庁に、先端犯罪の解明に有益な最新の捜査手法などの情報を提供しています。
▶back質疑応答・応援派遣
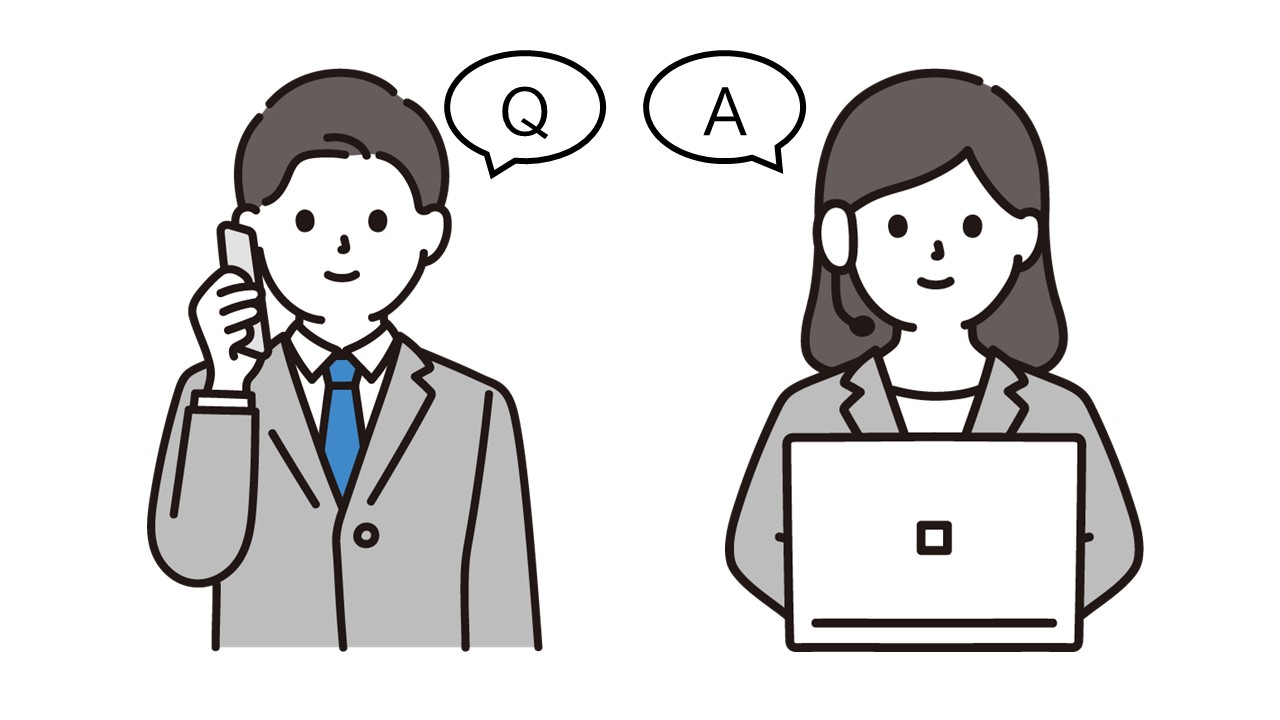
各検察庁からの専門的な問い合わせに対応するほか、複雑な事件には専門の検察官・検察事務官を派遣し、捜査・公判を直接サポートしており、各種サポート数は年間数百件に上ります。
専門的な知見や官民関係団体との幅広いコネクションを活かして全国の検察庁のサポートに当たっていますので、削除されたデータの復元や撮影画像の日時・撮影機器の特定、データ改ざんの痕跡の発見、不正アクセスのログの解析、犯罪に関係する暗号資産の追跡など、サポートの内容は多岐にわたっています。
▶back研修・教育

押収したスマートフォンやパソコン等に保存されているデジタルデータを適正な手続に基づき抽出し、抽出したデータを解析して犯罪立証のための証拠を見つける手法・技術のことを「デジタルフォレンジック(DF)」と言います。
こうしたDFやサイバー犯罪は、もはや専門家のみが知っていればよい領域ではなく、捜査・公判活動に従事する全ての検察官・検察事務官が相当程度の知識・技能を身につけることが求められる領域となっています。
そこで、JPECは、検察官・検察事務官等を対象に、全国の検察庁や官民関係団体から収集した専門的な知見を提供するとともに、実際に機器を操作するハンズオンに重点を置いた実践的な研修を数多く企画・実施しており、デジタル証拠の解析技術・分析手法や暗号資産・サイバー犯罪に関する最新の知識を習得することができるようにしています。
▶back機器整備(企画・立案)

先端犯罪捜査においては、一定水準以上のIT機器やソフトウェアを用いることが重要ですし、最新の高度なツールが必要な場合もあります。
JPECは、このような資機材の検察庁における導入・配備についても計画し、全国の検察庁の捜査・公判能力の向上を推進しています。
▶back関係機関・団体等との連携

多様化・複雑化する犯罪に対処するには、最先端の技術的知見の活用が不可欠です。
そこで、JPECは全国の検察庁のみならず、警察庁などの公的機関、IT企業・専門家といった民間団体や有識者からも最先端の技術的知見を積極的に収集しています。
また、JPECは、これらの関係機関・団体等と普段から緊密に連携し、安全で安心な国民生活を確保するために社会全体で先端犯罪に立ち向かう体制を構築しています。
▶back国際連携

サイバー空間での犯罪は、物理的な国境がないことから、犯罪行為が容易に国境を越えて広がり、証拠や関係者が外国に存在することが多々あります。
こうした場合に円滑・迅速に対応できるようにするとともに、諸外国の最先端の捜査手法や技術的知見に関する情報を収集するため、JPECは、諸外国の捜査機関と緊密に連携し、情報交換を図るとともに、諸外国で開催されているサイバー犯罪関係の国際会議に積極的に参加するなどして、関係強化に努めています。
▶back