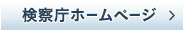死刑の執行は、法務大臣の命令により行われます。
- 検察庁
- 検察庁について
- 検察庁の業務
- 刑事事件の手続について
- 裁判の執行について
裁判の執行について
裁判の執行とは、国家の強制力により裁判の内容を実現することをいいます。
執行は、原則として、裁判の確定後速やかになされることとなっており、裁判を行った裁判所に対応する検察庁の検察官がするのが原則です。もっとも、刑の時効が完成したとき、刑の言渡しを受けた者が死亡したときなど、一定の事由がある場合には執行不能となり、執行されることはありません。
1. 死刑の執行
2. 自由刑の執行
自由刑には、刑務所内において改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる拘禁刑(無期及び有期があり、有期は1月以上20年以下です。ただし、加重する場合には、30年まで上げることができますし、減軽する場合には1月未満に下げることもできます。)などがあり、いずれも検察官が執行を指揮します。
(令和7年6月1日、刑法等の一部を改正する法律の施行により、懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されました。)
3. 財産刑などの執行
罰金(原則1万円以上で、これを納めることができないときは、1日以上2年以下の期間、労役場に留置されます。)、科料(千円以上1万円未満で、これを納めることができないときは、1日以上30日以下の期間、労役場に留置されます。)、没収などの財産刑のほか、追徴(没収ができないときに、その価額を国庫に帰属させる刑です。)、過料(商法違反や住民基本台帳法違反等に科される行政処分で、刑罰ではありません。)、訴訟費用(裁判に要した費用で、貧困のためこれを納めることができないときは、免除の申立てをすることができます。)、仮納付(罰金、科料、追徴について、裁判の確定前に執行を命ずる裁判です。)などの裁判は、検察官の指揮又は命令によって執行します。