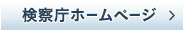検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事に区分されます。このうち、検事総長、次長検事及び検事長は、内閣が任免し、天皇が認証することとなっています。
地方検察庁には、検事の中から任命される検事正が置かれています。
- 検事総長は、最高検察庁の長として庁務を掌理し、かつ、全ての検察庁の職員を指揮監督しています。
- 次長検事は、最高検察庁に属し、検事総長を補佐し、検事総長に事故のあるとき、又は検事総長が欠けたときは、その職務を行います。
- 検事長は、高等検察庁の長として庁務を掌理し、かつ、その庁並びにその庁の対応する裁判所の管轄区域内にある地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督しています。
- 検事正(地方検察庁の長である検事)は、その地方検察庁の庁務を掌理し、かつ、その庁及びその庁の対応する裁判所の管轄区域内にある区検察庁の職員を指揮監督しています。
- 検事は、最高検察庁・高等検察庁及び地方検察庁などに配置され、捜査・公判及び裁判の執行の指揮監督などの仕事を行っています。
- 副検事は、区検察庁に配置され、捜査・公判及び裁判の執行の指揮監督などの仕事を行っています。
検察官は、次のような仕事をしています。
- 警察などから送致を受けた事件、検察官に直接告訴・告発のあった事件及び検察官が認知した事件について捜査を行い、これを裁判所に起訴するかどうかを決めます。検察官には、起訴できる事件でも、被疑者(犯罪を犯した疑いがあり、捜査の対象とされている者)の性格・年齢・境遇及び犯罪の軽重・情状などによっては起訴しないこと(起訴猶予)とする権限があります。
起訴処分には、法廷で裁判が開かれる公判請求と、これを開かずに書類審査で刑(罰金・科料のみ)が言い渡される略式命令請求があります。
なお、一定の重大な犯罪は、裁判員裁判の対象となります。 - 公判請求した事件の裁判に立ち会い、裁判所に証拠を提出したり、証人尋問などを行って、被告人(起訴された被疑者)が犯罪を行ったことなどを証明します(証拠調べ)。証拠調べの終了後、求刑を含む論告を行います。また、裁判所の判決に対して上級の裁判所に不服申立て(上訴)することもあります。
裁判員裁判では、検察官は、一般の国民から選ばれる裁判員が審理の内容を十分に理解し、容易に心証を形成できるよう、より分かりやすく、迅速で、しかも的確な立証に努めています。 - 裁判確定後、拘禁刑や罰金刑などの裁判が正当に執行されるように執行機関(刑事施設職員等)に対して指揮などをします。
- 公益の代表者として法令に定められた事務を行います。